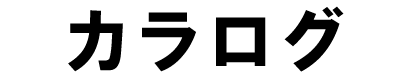谷川岳主脈縦走
[山域] 上信越 [CT] 11時間51分 [距離] 23.1km [登り] 2,732m [下り] 2,440m [日程] 日帰り
こんにちは。kara(@karalog2018)です。今回は前回の馬蹄形縦走に続き谷川岳縦走のお話です。第2弾となる今回は、上越国境稜線上に連なる山々を歩く「谷川岳主脈縦走」の山行です。
「谷川岳主脈縦走」は名前の通り、谷川連峰の名だたる山を紡ぐ道。谷川岳から万太郎山、仙ノ倉山、平標山までと、東から西へと歩きます。
スタートを谷川岳、平標山どちらからにするかがありますが、今回は東の谷川岳から。9月後半、あいにく紅葉ピークとはなりませんでしたが、すばらしい稜線、歩けましたよ。

02:40 AM 西黒尾根登山口

夜明け前の谷川岳

巻機山、越後三山方面はうっすら明るくなってきました
 ロープウェイからの道、天神尾根と合流
ロープウェイからの道、天神尾根と合流 天神尾根の先にはみなかみの街明かりが見える
天神尾根の先にはみなかみの街明かりが見える 肩ノ小屋にはあとから行きます。まずは山頂向かいましょう
肩ノ小屋にはあとから行きます。まずは山頂向かいましょう 谷川岳(オキの耳)山頂
谷川岳(オキの耳)山頂
05:39 AM 谷川岳の夜明け
 馬蹄形縦走のときに歩いた一ノ倉岳、茂倉岳方面
馬蹄形縦走のときに歩いた一ノ倉岳、茂倉岳方面 清水峠~朝日岳、うしろには巻機山や越後の山々も見える
清水峠~朝日岳、うしろには巻機山や越後の山々も見える
朝日に染まる上越国境稜線

トマの耳

オキの耳
 トマの耳、うしろには連なる谷川岳主脈の山々
トマの耳、うしろには連なる谷川岳主脈の山々 谷川岳(トマの耳)山頂
谷川岳(トマの耳)山頂
西黒尾根登山口から谷川岳
おはようございます。今日も前回同様「健脚向けコース」、長いコースと言うことで、日が昇る前、2時19分頃にスタートです。
白毛門登山口の駐車場に車を止めて、まずは谷川岳ロープウェイ土合口駅、その先、西黒尾根登山口まで進みましょう。
ちなみに今回は前回の馬蹄形縦走ような周回コースではないため、帰りに車を回収しに戻ってこなければなりません。谷川岳ロープウェイ近くにも駐車場はありますが、少しでもあとで登る距離を少なくするため、土合橋バス停近くの白毛門登山口駐車場を利用しました(その分はじめに「車道の登り」あるんですけどね)。
西黒尾根登山口からは樹林帯の急登。途中ガレ沢の頭を越えたあたりからは岩場が続きますが、何回か登っている道なので危なげなく天神尾根に合流できました。合流してしまえば谷川岳山頂、トマの耳とオキの耳までは目と鼻の先ですね。
こんにちは。karaです。今回はようやく書けた!去年7月に歩いた憧れの谷川岳馬蹄形縦走のお話です。「谷川岳馬蹄形縦走」は「馬蹄形」の言葉の通り[…][…]
こんにちは。燃えるような紅葉が見たい。kara(@karalog2018)です。いつも谷川岳は、夏山なら西黒尾根から、冬山なら天神尾根からと決まったコースで登っています。今回は「紅葉の時期はマチガ沢スゴイことになって[…]

06:05 AM 肩ノ小屋

谷川岳主脈縦走、上越国境稜線縦走開始です
 上越国境稜線南側の展望、台形の三峰山とうしろには赤城山
上越国境稜線南側の展望、台形の三峰山とうしろには赤城山 爼嵓と阿能川岳、さらに奥には吾妻耶山、榛名山まで見えている
爼嵓と阿能川岳、さらに奥には吾妻耶山、榛名山まで見えている 爼嵓山稜(左)とオジカ沢ノ頭(右)
爼嵓山稜(左)とオジカ沢ノ頭(右) 上越国境稜線北側展望、茂倉岳と一ノ倉岳
上越国境稜線北側展望、茂倉岳と一ノ倉岳
まずはオジカ沢ノ頭へ向かいましょう
 タカネコンギクかな?
タカネコンギクかな? いくつかあった「マツダ」ランプの標柱
いくつかあった「マツダ」ランプの標柱
谷川岳を振り返る。肩ノ小屋から結構くだってきましたね

オジカ沢ノ頭を登りましょう(クサリ場もあります、ご注意を)

06:54 AM オジカ沢ノ頭

オジカ沢ノ頭(標高1,840m)
谷川岳山頂で日の出を迎えたら、いよいよ谷川岳主脈縦走、上越国境稜線縦走を開始しましょう。
まずは肩ノ小屋から、いつも見ている爼嵓(まないたぐら)、オジカ沢ノ頭方面へ大きく下りながら進んで行きます。
途中には真っ赤に目立つ「マツダランプ」の標柱ありました。このランプの標柱は上越国境稜線上にいくつかありましたが、谷川岳近くは「マツダランプ」で平標山近くは「東芝ランプ」なんですよね(おもしろい)。
肩ノ小屋から下り切ったらオジカ沢ノ頭への登りです。思ったよりも登ります。途中にはクサリがあったりすこし細尾根なので気を付けましょう。

爼嵓山稜

本当の谷川岳「爼嵓(まないたぐら)」
オジカ沢ノ頭からは2つの道に分岐します。これから向かう平標山までの尾根道と、俎嵓山稜の尾根道です。
今回は行きませんが俎嵓山稜の主峰「俎嵓(まないたぐら)」は、以前は「谷川岳」と呼ばれていたそうです。いつの間にか今のトマの耳、オキの耳の方の「谷川岳」に名前を取られちゃいましたが、いつかはコチラの「旧谷川岳」にも登ってみたいと思います。
登るコースとしては、オジカ沢ノ頭から藪漕ぎしながら夏に進むか、積雪期、藪が埋まったころに登りにいくか。いずれにせよ正式な登山ルートではないので難易度はそれなりに高そうです。
積雪期と言えば、肩ノ小屋とは別のルートで爼嵓山稜縦走の記録がありました。
- 仏岩ポケットパーク(吾妻耶山登山口)~鍋クウシ山~三岩山~阿能川岳~小出俣山~本谷ノ頭~川棚ノ頭~爼嵓~オジカ沢ノ頭~谷川岳
- 川古温泉~十二社ノ峰~松ホド山~三尾根岳~小出俣山~本谷ノ頭~川棚ノ頭~爼嵓~オジカ沢ノ頭~谷川岳
どちらも積雪期限定のルートなのかな?1泊2日以上が妥当な玄人好みのルートのようですが、いくならまずは、肩ノ小屋からかな。
そうそう、俎嵓山頂には聖剣エクスカリバーよろしく「伝説の鎌」(草刈り用の鎌)があるそうです。そう言うの聞くと、ますます行ってみたくなりますよね~(笑)。
 06:59 AM オジカ沢避難小屋
06:59 AM オジカ沢避難小屋 避難小屋内部はこんな感じ
避難小屋内部はこんな感じ
上越国境稜線の続き、万太郎山へ

爼嵓山稜を横目に進みます
 なにか標柱見えてきましたね
なにか標柱見えてきましたね 07:22 AM 小障子ノ頭
07:22 AM 小障子ノ頭
小障子ノ頭(標高1,730m)
話は戻ってオジカ沢。谷川岳主脈を行くには俎嵓じゃない方、小障子ノ頭へ向かいます。
オジカ沢ノ頭降りて少し進んだところには馬蹄形縦走でも何度か見かけましたね、カマボコ形、ドラム缶の避難小屋。谷川岳ではこれがデフォルトなのかしら。
避難小屋からは一旦下って、小障子ノ頭へ登り返します。まだまだ前半と言うこともあって、また絶景も相まって疲労は少なめ。ただ前日雨だったからか足元が笹やなにやらでビショビショで、そこがちょっとマイナスでしたね。

小障子ノ頭から次は大障子ノ頭

カマボコ形の避難小屋がまた見えてきた
 07:33 AM 大障子避難小屋
07:33 AM 大障子避難小屋 お邪魔します
お邪魔します
大障子避難小屋と谷川岳まで続く稜線。左後ろには茂倉岳から一ノ倉岳も見える
 トリカブト
トリカブト イワショウブの実。花は白いらしい
イワショウブの実。花は白いらしい
最高の一日。天候に恵まれました

ところどころ草紅葉してますね(イイ感じ)

歩いてきた道。アップダウンありますが、基本は下ってきているみたいです
 一転、大障子避難小屋から万太郎山まではキツイ登りが続きます
一転、大障子避難小屋から万太郎山まではキツイ登りが続きます 07:52 AM 大障子ノ頭
07:52 AM 大障子ノ頭
大障子ノ頭(標高1,800m)
「小」の次には「大」がある。小障子ノ頭から大障子ノ頭へ。途中にはまたおなじみのカマボコもとい避難小屋がありました。
主脈縦走通して見ると、馬蹄形縦走より小屋の数は多かったですね。馬蹄形では笠ヶ岳、清水峠、蓬峠に一ノ倉岳、4つですね。対して主脈はオジカ沢、大障子、越路、エビス大黒、平標山と5つ。
あれ?書いてみたら意外と数は変わらない。むしろ馬蹄形は進行ルート上にはありませんが茂倉岳にもあるので同数ですね。あれこれ今思い出して書いていますが、小屋と小屋の間隔が主脈縦走の方が近い(近く感じる)から多くあるように思えるのかしら。
主脈縦走はピークとピークの間にほぼ小屋があるのに対し、馬蹄形縦走は(白毛門からはじめると)前半にはほぼほぼ小屋ありませんから(笠ヶ岳くらいですね)。
小屋の話ばかりしてしまいましたが、大障子ノ頭は「下り」にご注意を。万太郎山側に下るところは岩場の急坂。雨が降ったあとで岩が濡れていて、かなり神経消耗しました。

そびえ立つ万太郎山

今回一番のシンドイポイント「万太郎山の登り」

休み休み登ります。写真は振り返っての大障子ノ頭~小障子ノ頭。茂倉岳から谷川岳までも良く見える

万太郎山ビクトリーロード(まだちょっとあるけど)

万太郎山から見た谷川岳方面の展望。ここからの景色が今回の山行で一番好きです
 山頂標識、倒れてる!?と思ったら少し先になにかありそうですね
山頂標識、倒れてる!?と思ったら少し先になにかありそうですね コチラが本物の万太郎山山頂標識
コチラが本物の万太郎山山頂標識
万太郎山からは吾策新道をつかって土樽に下りれるそうです

万太郎山山頂(標高1,954.1m)
大障子ノ頭の難所、下りの岩場をクリアしたら、ここからは怒涛の登りの万太郎山(サゴーノ峰)。
振り返り見る谷川岳までの稜線、今まで歩いた稜線は「絶景」の一言なのですが、いかんせん登りがダルすぎる。個人的にはここで一気に疲れがきちゃいました。
やすみやすみなんとか万太郎山を登りきると、そこには折れた標識が。正直「こんなに難儀しながら登ってきたのに、なんてご無体なことしてくれる」と怒り通り越して笑ってしまっていたのですが、そこから少しだけ先へと進んで行くと、良かった、ちゃんとした万太郎山山頂標識ありました。

万太郎山から見た展望
 右手には仙ノ倉山。あそこまでこれから歩いてゆくのか
右手には仙ノ倉山。あそこまでこれから歩いてゆくのか 痩せた尾根を通ります。雪とかあるときはいやらしそう
痩せた尾根を通ります。雪とかあるときはいやらしそう
振り返って、万太郎山越しに見る谷川岳。猫耳は目立ちますね(笑)
 仙ノ倉山へは、東俣ノ頭まで行かず手前を曲がってくだります
仙ノ倉山へは、東俣ノ頭まで行かず手前を曲がってくだります ミヤマアキノキリンソウ(たぶん)
ミヤマアキノキリンソウ(たぶん)
エビス大黒ノ頭、仙ノ倉山。カッコ良いですね

振り返って万太郎山。こんなところをくだっています(下りすぎ感はあります)
 ハクサンイチゲ
ハクサンイチゲ ヤマハハコ
ヤマハハコ 避難小屋が見えてきましたよ!
避難小屋が見えてきましたよ! 09:33 AM 越路避難小屋
09:33 AM 越路避難小屋 ハクサンフウロ
ハクサンフウロ アザミ
アザミ
越路避難小屋から最低鞍部にある毛渡乗越へ
 09:53 AM 毛渡乗越(越路)
09:53 AM 毛渡乗越(越路) 毛渡乗越からは仙ノ倉山手前のエビス大黒ノ頭をまず目指します
毛渡乗越からは仙ノ倉山手前のエビス大黒ノ頭をまず目指します 振り返って万太郎山。写真中央のとがったところから歩いてきたんですよ!
振り返って万太郎山。写真中央のとがったところから歩いてきたんですよ! いくつかのピークを越えて
いくつかのピークを越えて 我、エビス大黒ノ頭、到着ス
我、エビス大黒ノ頭、到着ス 10:57 AM エビス大黒ノ頭
10:57 AM エビス大黒ノ頭
エビス大黒ノ頭(標高1,888m)
万太郎山から次は、仙ノ倉山ではなくて。その前に、目の間にそびえる(まさにそびえる)「エビス大黒ノ頭」を登ります。
ただ登るだけなら良いのですけどね、ここからはまたもや下ります。且つ今回の山行の中では一番大きな下りです。一気に最低鞍部、標高1,568mにある毛渡乗越(越路)まで下ります。
ちなみにエビス大黒ノ頭のうしろにある仙ノ倉山は、なんということでしょう!谷川連峰最高峰の標高2,026,3m!
一気に標高差458.3mを登るのです。まあ、高尾山の標高差が400mくらいらしいので、今から「高尾山」登るって考えれば良いのです。山ヤなら余裕ですよね?高尾山。たかが高尾山、されど高尾山。
わたしはゾーンに入っていたんですかね、万太郎山ではヘロヘロでしたがエビス大黒ノ頭、意外と普通に登れちゃいました。
何度か偽ピークらしきものもありましたが、「どうせこれ偽エビスとか前エビスだろ」と思いながら登っていたのでそこまで精神的なダメージも追わず、エビス大黒ノ頭まで行けました(笑)。

エビス大黒ノ頭から見た仙ノ倉山。また一回くだってますね?

でもここが大詰め。仙ノ倉山の最後の急登です!
 11:29 AM エビス大黒避難小屋
11:29 AM エビス大黒避難小屋 エビス大黒ノ頭を振り返る
エビス大黒ノ頭を振り返る
あせらずじっくり。仙ノ倉山山頂へ向かいましょう

万太郎山(左)とエビス大黒ノ頭(右)
 仙ノ倉山、山頂付近はちょっぴり紅葉してました
仙ノ倉山、山頂付近はちょっぴり紅葉してました シッケイノ頭とうしろには湯沢の街
シッケイノ頭とうしろには湯沢の街
仙ノ倉山山頂(標高2,026.3m)
エビス大黒ノ頭からは最後の急登です。がんばりましょう。正確には平標山山頂手前でも登りはありますが、本格的な急登はここが最後。山は逃げないのでじっくりゆっくり確実に、山頂目指して登りましょう。
エビス大黒ノ頭からはちょうど1時間くらいでしょうか。谷川連峰最高峰「仙ノ倉山」登頂です。
谷川連峰ってどの山もスケールが大きく迫力満点なのですが、意外にも2,000m越えているのはこの仙ノ倉山だけなのですね。お隣、平標山は1,983.8mですし、谷川岳(オキの耳)についてはさらに低い1,977mなのですよ。
三国山脈まで範囲を広げれば2,000m越えはいくつかあるようですが、わたしは三国山脈はあまり馴染みがないのです。コチラもいつかじっくり調べてみよう。
ちなみに今回初めて知ったのですが、仙ノ倉山北尾根、積雪期限定で登れるようです。土樽駅のあたりから、シッケイノ頭経由で登るようです。平標山のヤカイ沢のコース同様、「限定」と言う言葉に惹かれちゃいますね~。
こんにちは。今考えると秋は天気に恵まれてたのね、それに比べて冬はなかなか晴れんのう。kara(@karalog2018)です。※今回の山行は前回の谷川岳近くになりますね。平標山・仙ノ倉山のお話です。平標山・仙ノ倉山と[…]
こんにちは。kara(@karalog2018)です。今回は大好きな谷川連峰の西側になりますかね、平標山と仙ノ倉山の山行です。3月の登山と言うことで、いつもの松手山コースからではなく【積雪期限定】のヤカイ沢からのコースで登ってみました。 [[…]

仙ノ倉山から最後の平標山へ
 12:12 PM 前仙ノ倉山
12:12 PM 前仙ノ倉山 仙ノ倉山~平標山間の天国のような稜線
仙ノ倉山~平標山間の天国のような稜線 木道、好きです(また言ってる)
木道、好きです(また言ってる) 「東芝」ランプ
「東芝」ランプ
平標山ビクトリーロード。最後の登りです

平標山から見た仙ノ倉山。ここ好き

平標山山頂(標高1,983.8m)
仙ノ倉山から平標山は、広い尾根に木道が通るとても気持ちの良い稜線です。夏であればお花畑が広がりますし、秋は草紅葉がとってもステキ。
谷川岳主脈縦走の最後を飾るにふさわしい、わたしも大好きな山なのです。「主脈縦走はちょっとキツイ」と言う方でも単体で登っても十分満足できる山なので、季節を問わず登ってほしい、ほんと良い山なのです平標山は。
こんにちは。明日、とたけけやってきます。絶賛あつ森ハマり中、kara(@karalog2018)です。今回は、以前平標山・仙ノ倉山に登った時に気になっていた【残雪期限定の山】日白山のお話です。残雪期限定と言うだけあっ[…]

平標山から下山しましょう
 13:08 PM 平標山の家
13:08 PM 平標山の家 13:34 PM 平元新道登山口
13:34 PM 平元新道登山口 13:57 PM 上信越自然歩道「岩魚沢林道」のゲート
13:57 PM 上信越自然歩道「岩魚沢林道」のゲート 14:09 PM 平標登山口バス停
14:09 PM 平標登山口バス停 14:20 PM 平標登山口から湯沢駅前へ
14:20 PM 平標登山口から湯沢駅前へ JR上越線で越後湯沢駅から土合駅へ
JR上越線で越後湯沢駅から土合駅へ
谷川連峰の主脈を繋ぐ「谷川岳主脈縦走」下山です。
平標山からの下山ルートはいくつかあります。わたしは慣れたコース、途中に「平標山の家」がある平元新道のルートを選びましたが、みなさんは用途にあわせて選んでみてください。
- 下山2時間25分 松手山~平標登山口
- 下山2時間30分 平元新道~上信越自然歩道~平標登山口
- 下山4時間00分 平標新道~土樽駅
尚、今回の山行はある意味下山もポイント(勝負)です。と言うのも、スタート地点である土合駅になんとかして帰っていかなければならない。
わたしの使った平元新道、松手山のルートの場合は「平標山登山口」に下山するのですが、その場合はまず「湯沢駅前」までバスに乗って、そこからJR上越線に乗って「土合駅」まで。
難易度をあげているのがバス、電車ともに本数がかなり少ないと言うところ。下にざっと11時以降のものをまとめてみましたが、1本乗り過ごすだけで大変なことになっちゃいます。わたしは運よく14時20分のバスに乗れましたが(最後の林道は小走りでした)、乗り遅れていたら2時間待ちだったという話ですね(恐ろしや)。
そう言う意味だと平標山からの下山時間は長くなりますが、体力に自信があるなら平標新道からの下山も「アリ」かもしれません。増水時注意な渡渉ポイントはありますが、直接土樽駅に下りれるというのは「バスに乗らなくてよい」ということでもあるので時間調整しやすいのかも。
南越後観光バス
| 平標登山口 | 湯沢駅前 |
| 11:45 | 12:23 |
| 13:00 | 13:38 |
| 14:20 | 14:58 |
| 16:55 | 17:33 |
※2023/11/2時点の時刻表から抜粋
JR上越線 水上・渋川方面 (上り)
| 越後湯沢 | 土合 |
| 15:08 | 15:33 |
| 15:19 | 15:48 |
| 17:52 | 18:18 |
※2023/11/2時点の時刻表から抜粋
なんにせよ無事、上越国境稜線、谷川岳主脈縦走完了です。
谷川岳馬蹄形、谷川岳主脈と憧れていた2つの稜線をケガもなく、また天気の良い中歩けたというのは本当によかったと思います。
最後に、個人的な見解にはなりますが、
- 難易度/体力度としては、「谷川岳馬蹄形縦走 > 谷川岳主脈縦走」でした。
- 満足感としては、(甲乙つけがたいですが、これもどちらかと言うと)「谷川岳馬蹄形 > 谷川岳主脈」でしたかね。
馬蹄形縦走の方が暑くて大変だった分、思い出深いのかもしれません。
次また谷川岳に登るなら、馬蹄形を秋に、主脈を夏に歩いてみようかな。それとも雪の季節に本当の谷川岳「爼嵓(まないたぐら)」を登りに行ってみようかな。
7月に馬蹄形縦走をやっていたので、今年のうちに主脈縦走も、ということで台風一過の快晴の中、谷川連峰歩いてきました。雨…